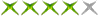壓克力車體的電源行李車製作說明
我現在時間不多,還不能翻譯中文。
*********************
 ***************
***************台湾の電源荷物車です。
呂光号、復興号に連結されています。 塗装は呂光号色のみ存在します。
製品説明:
車体キット
キット構成:
側面、妻板、屋根上機器一部、床板、床下機器一部/アクリル
屋根/木製
縮尺及びゲージ:16番 1/80 16.5mm
製造:佐藤商会.日本
摘要年齢: 13歳以上、鉄道模型の知識が無い方にはお勧めできません。
事前予告無く、内容が変更されることが有ります。 ご了承ください。
使用塗料:
GMカラー 4/クリーム4号、8/銀、10/黒、14/灰色9号、31/朱4号、35/ダークグレー、37/白3号
屋根用下地塗料:サンディングシーラー(模型店ではなく、DIYにあります)
塗装はピースコンでも缶スプレーでも構いません。
製作:
1. 側面の表面(文字や黒い線が入っている)の保護紙を剥がしてください。角にカッターナイフをあてると簡単に剥がれます(アクリルは傷つきません)。
堶はドア、妻、3mm角材と接着する部分に切れ目を入れて剥がしてください。
2雨樋(1mm帯材)を接着します。
側面を平らなところ(平らな板が良い)に置き、セロテープなどで固定します。
雨樋を割り箸などで帯材を抑え,細筆に専用接着剤を含ませて流します。
端から少しずつ進ませます。完全に接着しているか確認後、余分を切り落とします。
3ドア
保護紙は窓とを残してはがします。
1) 車端部
1段凹んでおりますので、L字型のパーツを接着してから側面に接着します。
側面堸も接着部は当然保護紙は剥がしてください。
2) 荷物室ドア
Hゴム付きと角型の2種類各2枚同封しております。お好みによってお決めください。側面にそのまま接着します。
3) 機関室ドア(両開き)
同様、側面に接着します
4) 機関室乗務員ドア(片開き)
これは片方のみのですので1枚だけです。
4妻板
外、内張各2枚有ります。
内張は貫通扉を兼用しています。
保護紙は内張の内側を除き全部剥がしてください。内張りの内側は左右各2mmにカッターで筋をつけ、外側を剥がします。
5.側面ルーバー
波状のシートが入っています。これを切断して側面の堸から貼り付けます。
荷物室ドア両側の部分のみガラスですので、ここには付けません。
別図をご参照ください(ルーバーは左右同じ)
また乗務員扉が無い方は機関室となっており、波板を縦に接着します。
6角材
上下左右、4箇所に接着します。 角材はアクリルでも木製でも構いません。
側面上部は屋根板とののりしろをかねますのでツライチにしてください。
下は床板がきますので、裾から3mm上がった位置にします。
接着はアクリルであれば専用接着剤、木製や金属の場合はゴム系が適しています。
7組立
妻と側面を組み立てます。妻だけの支持では弱いので2.5mm穴が開いている1mm厚の板を使用します。
下3箇所、上2箇所です。
組みましたらズレがないかチェックしてください。
8.屋根上ルーバー部の組み立て
0. 5mm厚:35x29mmと8x29mm
1. 0mm厚:16x8mm
と、プラ板または表面が平滑な紙を”17x29mm”に切り出し、箱に組み立てます。
8x29mmの内側に適当な角材をつけると組み立て易くなります。
組めましたら側面に波板を切り出して貼り付けます。
9.床下機器
燃料タンクのみアクリル板から組みます。 他は市販の床下機器(エアータンク等)をご利用ください。
10屋根板
ルーバー部を挟み2枚に切断します。
・ 電源室側(短い部分):61ミリ
・ 荷物室側(長い部分):152ミリ
ただし、手作業が多いので、現物に合せると若干誤差が生じる可能性がありますので耐水ペーパーで調整ください。
また妻板に比較し、屋根の方が若干大きいので耐水ペーパーで成形してください。
成形前にセンターを出し、ベンチレーター穴を開けます。
穴の位置は別紙図ご参照下さい。
その後、“サンディングシーラー”で目止めを行います。
最初濃い目で刷毛塗りします。
乾燥したら研磨
それを何度か繰り返し、最後は吹き付けで行います。
本塗装(灰色)前に、プラ板または表面が平滑な紙を”20X38mm”に2枚切り出し屋根板に接着します(発電機器、エンジンの開口部)。
屋根と屋根上ルーバー部は暗ら目の灰色です。塗装は同様吹き付けで行ってください。
車体に仮止めし、ネジ穴を開けます。
屋根板は側面の塗装後に接着剤とネジ止併用で行って下さい。
11屋根以外の塗装
実車写真をご参照ください。
実車写真をお持ちでない方は弊社URLまたは人人出版の書籍をご参照下さい。
灰色(車内色)、白と塗装します。やはり吹き付けです。
白塗装後1.5mm幅マスキングテープを使用し帯部分をマスキングします。
その後オレンジを塗装します。
オレンジが乾燥したら斜め塗装、窓下を注意し、マスキングの上、クリーム塗装を行います。
サッシ窓部分は窓部分、の保護紙を剥がさず、銀塗装します。
塗装後の窓部分と本体はゴム系接着剤で取り付け下さい。
下周りは、エンドビーム、ステップを含め、黒塗装です。
塗装後台車、連結器をつけてください。
連結器位置は現物合わせの方が正確です。
付属の幌は車体と同じ色か黒で塗装ください。
なお、現在欧州式幌にかわりつつありますが、これは他社(外国)製品を使われるか、プラ板より削り出して下さい。
12.テールライト
付属の光学繊維(赤)と円盤を使います。
円盤は赤塗装して下さい。
ライター等を使って光学繊維の頭をレンズ状態にします。
本体との接着はゴム系をご使用ください。
以上は、あくまで基本ですので、各自でアレンジされることをお勧め致します。
別売品:
TR62台車(日光)、センターピン+ボルスター(日光)
、ベンチレーター(エコー)
、連結器(KD)
、3mmアクリル角材、0.3mm、0.5mm、1mmプラ板(田宮)少々
*********************************************************